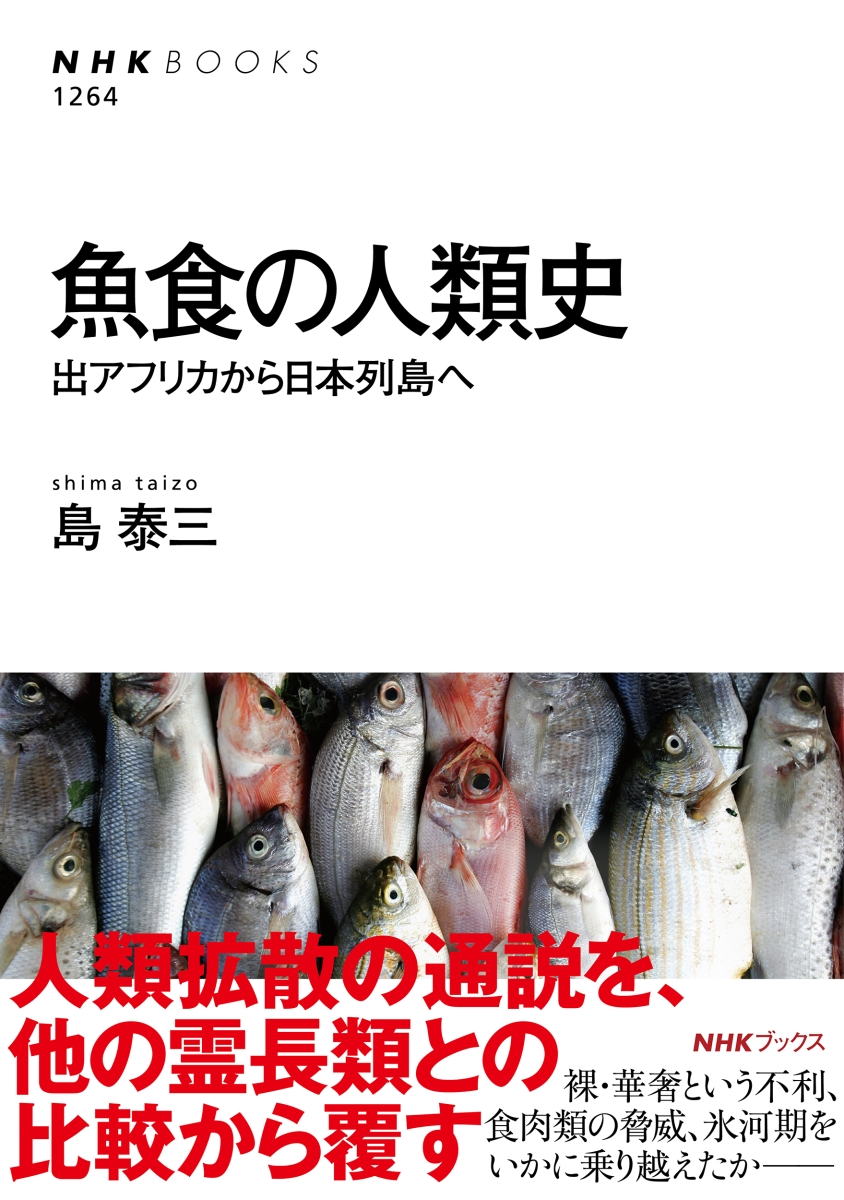
魚食の人類史
出アフリカから日本列島へ
NHKブックス No.1264 1264
島 泰三
2020年7月27日
NHK出版
1,540円(税込)
科学・技術
裸の皮膚、華奢な骨格、平らな歯列ー。ホモ・サピエンスのこうした特徴は、必ずしも生存競争に向いているとは言えない。その不利を覆し、人類に繁栄をもたらしたのが「魚食」だった。人類は、魚食によってホモ・エレクツスやネアンデルタールら、陸の王者との競合を避け、アフリカから拡散していく過程で、飢えを満たし、交通手段を発展させ、新たな文化を生み出した。果たして、それは一体どのようなプロセスであったのか?他の霊長類との比較、最新の人類史研究の成果を総動員し、やがて日本列島へと至る「大逆転の歴史」を鮮やかに描き出す。
本棚に登録&レビュー
みんなの評価(2)
starstarstarstar
読みたい
2
未読
0
読書中
2
既読
3
未指定
4
登録しました。
close

ログイン
Readeeのメインアカウントで
ログインしてください
Readeeへの新規登録は
アプリからお願いします
- Webからの新規登録はできません。
- Facebook、Twitterでのログイ
ンは準備中で、現在ご利用できませ
ん。
シェア
X

LINE
リンク
楽天ブックスサイト
楽天ブックスアプリ
© Rakuten Group, Inc.
キーワードは1文字以上で検索してください




toruo
(無題)
なぜ霊長類の中でもホモ・サピエンスだけが積極的に魚を食べるのか、という帯に惹かれて手にとってみた。 学者さんの作品らしく最初は読みにくいな、と思ったのだけど…なんというかくどいんだよね。「積極的に」というところがミソで例えば干上がった池で魚を拾って食べる猿は確かにいるのだけど…みたいなのが続くとちょっとめんどくさくなるんだけどそこを抜けるとかなり興味深い言説が現れる。屈強で身体能力も知力も高かったネアンデルタール人と比べて非力なホモ・サピエンスは水際に追いやられやむなく魚を獲って食べ始めたところから発展が始まったのではないか、という話。発掘された人類の歯型から何を食べていたのかを推測したりするのだけど側面的に補強する検証の過程が楽しい。例えば農耕はメソポタミア地方で穀物の栽培から始まった、という定説に対して、いきなり穀物はハードルが高い、例えば稲作は苗床を作ったり収穫しても脱穀したりなんやかんやと手がかかるのだけど、作者はアジアで魚食から始まって水際でタロイモのようなものを栽培するところから始まってそこから同じく水辺に生えていたイネを育て始めたのが農耕の始まりではないかという提起をする。面白いのは、というと不謹慎だけど太平洋戦争中に孤立した日本軍の手記からも、例えば最初はバナナを発見してそればかり食べているのだがカリウム摂取過多で体調を崩して他の食糧を探す中で原始的な釣り竿を作ってみると慣れていない魚が餌をつけなくてもたくさん採れた、とかそういう話も引用して説を補強していくところなどが興味深い。そもそも脳が大きくなったのもEPA/DHAの摂取が効いているのでは等々、非常に興味深かった。もう少し読みやすくするとよいのに、という印象。
全部を表示 いいね0件
いいね0件