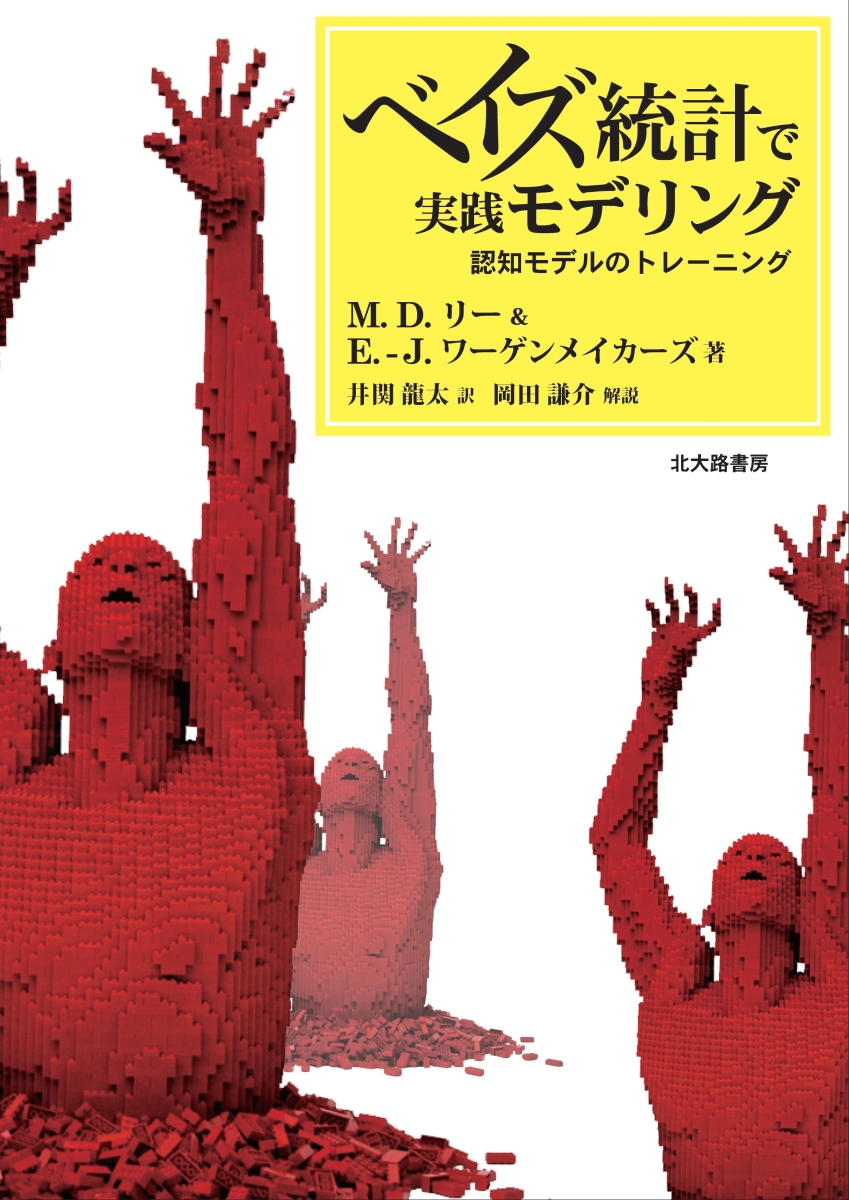
ベイズ統計で実践モデリング
認知モデルのトレーニング
M.D.リー / E.-J.ワーゲンメイカーズ / 井関 龍太 / 岡田 謙介
2017年9月28日
北大路書房
3,960円(税込)
人文・思想・社会
本棚に登録&レビュー
登録しました。
close

ログイン
Readeeのメインアカウントで
ログインしてください
Readeeへの新規登録は
アプリからお願いします
- Webからの新規登録はできません。
- Facebook、Twitterでのログイ
ンは準備中で、現在ご利用できませ
ん。
シェア
X

LINE
リンク
楽天ブックスサイト
楽天ブックスアプリ
© Rakuten Group, Inc.
キーワードは1文字以上で検索してください




みんなのレビュー